こんにちは。エンジニア大学編集部です。
前章では、条件式の組み合わせ方法について学びました。
本章では、switch文について学びます。
switch文とは
例えば、1等から3等までのくじがあったとします。
これまで学習した条件分岐を用いて、引いた数字に対して結果を出力する場合、以下のようなコードになるかと思います。
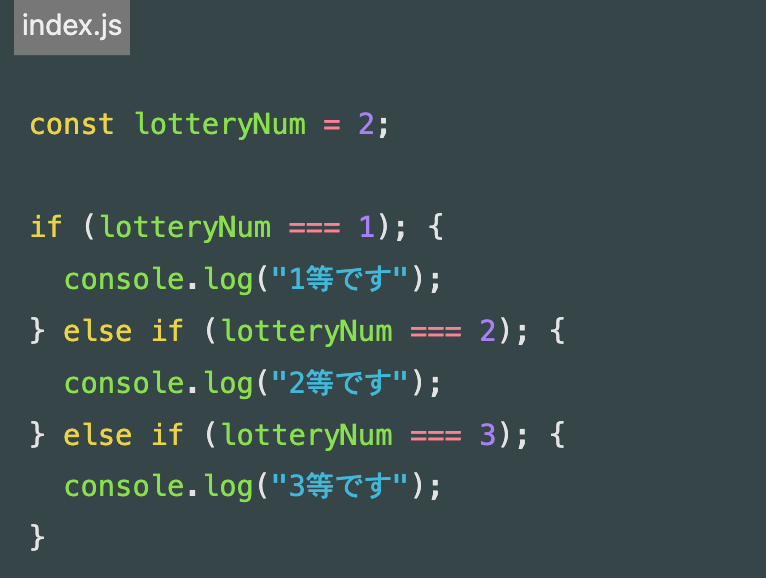
定数lotteryNumにくじ引きで引いた番号を格納し、条件分岐で引いた番号ごとに出力結果を変えています。
ですがこれだと、可読性が悪く、見づらいコードになってしまいます。
また、くじの数が10等まであった場合、記述量が多くなり大変です。
そんな時に使用するのが「switch文」です。
くじのコードをswitch文で記述すると以下のようになります。
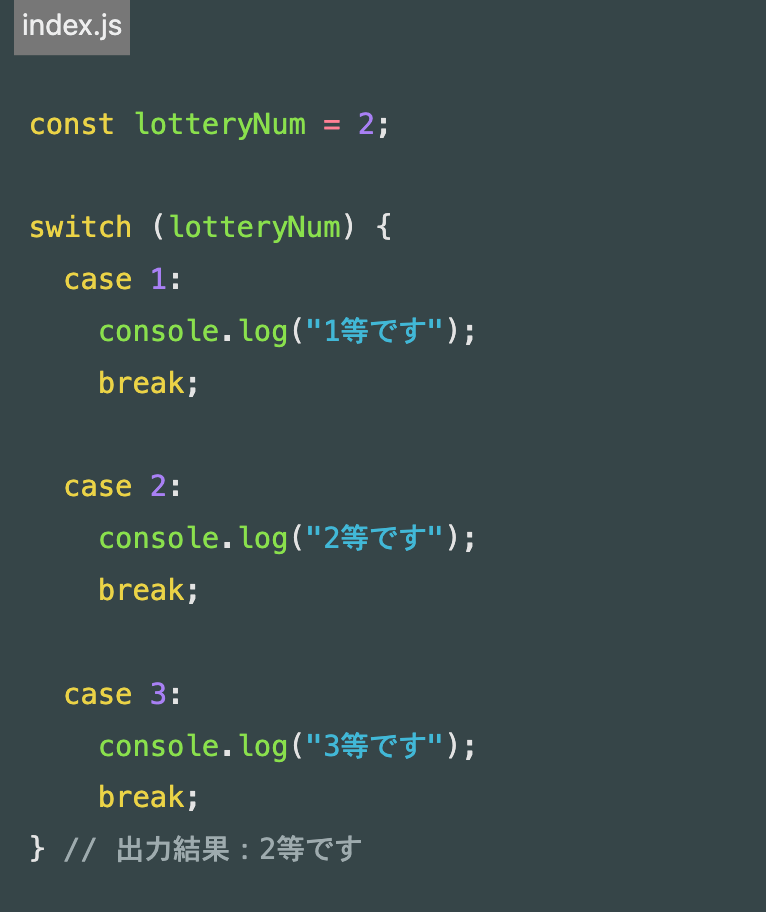
先ほどより、かなり見やすくなりました。
上から説明していきます。
「switch」は、「今からswitch文作ります」という宣言です。その後の()内に、条件として使用する値を入れます。
「case 1:」は条件式です。「case 〇〇:」という形で、〇〇の中に条件式を入れます。条件に対してtrueの場合のみ、次行のconsole.logが実行されます。
今回、lotteryNumに格納されている値は「2」なので、case 2でtrueが返されます。
「break」は、switch文を終了する命令です。breakがないと、合致したcaseの処理を行なった後、その次のcaseのプログラムも実行されてしまいます。必ず各caseにbreakをつけましょう。
まとめ
本章ではswitch文について学びました。
条件分岐の中でも、switchを使う場面はとても多いです。
次章でもswitch文について学んでいきます。まずは本章をしっかり抑えて、次章へ挑みましょう!
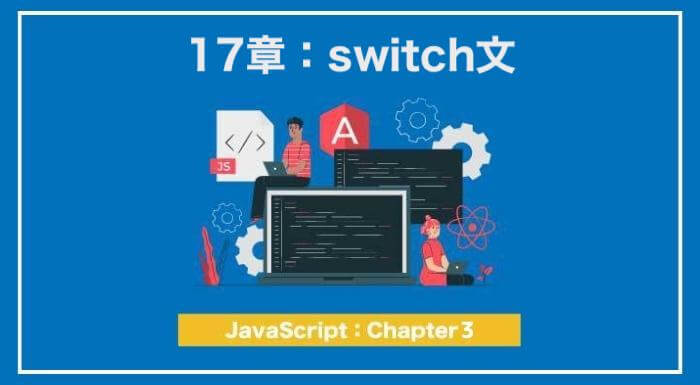
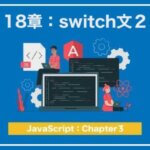
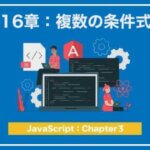

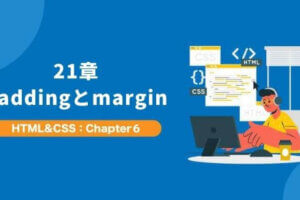


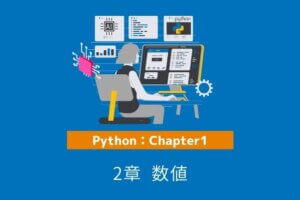




コメントを残す